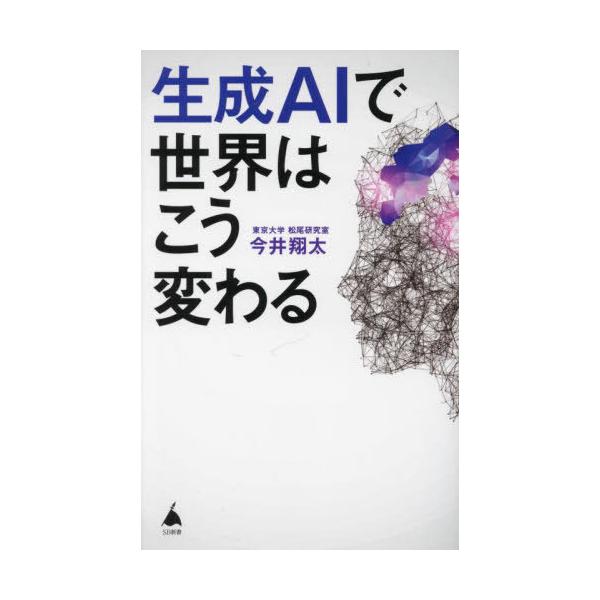
現状を把握するために
今まで読んだAI関連本の中では、一番わかりやすく、まとまりがあり、現状を把握できる本だと感じた。
2024年1月15日に出版されている本なので、2022年11月にChatGPTが公開されてから、1年あまりの状況を基に書かれている。
現在(2025年8月24日)は、それから1年半ほど経過しており、ChatGPTはGPT-5になり、Geminiはマルチモーダルで使えるようになっている。
生成AIは、無料でつかえることで膨大なユーザーを獲得し、開発は加速してマルチモーダルになり、リアルタイムの検索情報も含めた対応ができるようになり、留まるところを知らない。
音声でプロンプトを与えて、テキスト・画像・動画・音声を交えた回答ができるようになるまで、それほどの時間を待たず実現可能になるだろう。
世の中の状況は、今年の末にはこの本の増補版が出るくらいの勢いかもしれない。
GPTs are GPTs
2023年11月にChatGPTが公開された時、友人からチャットでGPTは何の略か聞かれたことがあった。その時、適当に検索して、「General Purpose Technology」と答えたことがあった。
その後、他の友人から違うだろ、「Generative Pre-trained Transformer」と言われ、恥ずかしい思いをしたことがあった。
この本を読んだら、なんで間違ったのか、何となく原因がわかった。
以下の論文がその原因。
「GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models」
このときは、間違ったと思って、それ以上深く考えたことがなかった。しかし、「言語モデルの生成AIが汎用技術である」という言葉の意味が、重要であることに今頃になって気がついた。
研究者とクリエイターに与える影響
生成AIに関する本で必ず出てくるのが、「消える仕事・残る仕事」という話題です。
ブルーカラーよりも、ホワイトカラーの仕事が大きな影響を受けるという話は、どの本でも取り上げていますが、著者が研究者であるため、「研究者とクリエイター」について、書いているのが面白いと思いました。
また、機械学習するために、インターネット上のコンテンツを利用することに関して法律上問題ないのか、現在の状況が書かれていました。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。