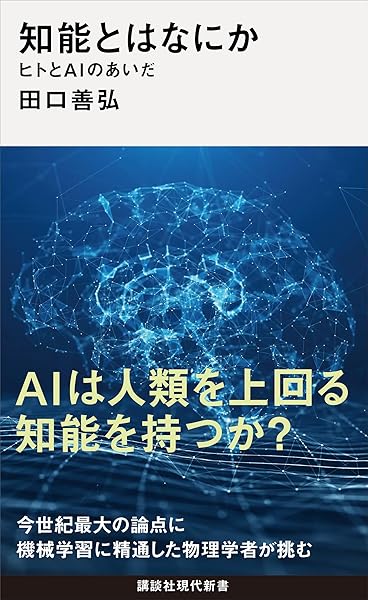
本の紹介
「元非線形非平衡多自由度系」物理学者による知能とAIの一般向け解説書。
機械学習に精通する著者が、一般向けにざっくり説明を書いていて、2025年現在のAI研究の現状を大枠で理解することができる。
各章にコラムがあり、その内容がとても面白い。
これだけでも読む価値がある。
- GPUと生成AI
- 日本人がとってもおかしくなかったノーベル物理学賞
- 機械学習いろいろ
- ブレイン・マシン・インターフェース
- BERT
- 目覚ましい成果を上げるディープラーニング
- アンコンシャス・バイアス
- コンピュータチェス、将棋、囲碁
- 自律型AI
- リザーバコンピューティング
私がこの本で面白いと思ったこと
以下3点。
- Ai研究の歴史や機械学習に精通した著者であっても、膨大なパラメータを持ったChatGPTが、過学習を逃れている理由がわからない。
(過学習とは、機械学習モデルが訓練データに過剰に適合し、未知のデータに対する予測精度が低下する現象です。訓練データに対しては高い精度を示すものの、実際の運用で使われるデータに対しては性能が発揮できない状態を指します。)
ChatGPTのソースが非公開なのは、そのノウハウを秘密にしたいのかもしれません。 - 著者は、機械学習に精通し、「非線形非平衡多自由度系」の研究を行い、生成AI研究がすぐそばにあったにもかかわらず、素通りして、大きなチャンスを逃してしまった、と悔やんでいること。
チャンスはそばにあっても気が付かないのが普通です。セレンディピティがついて回るのは、その人の才能です。 - OpenAI ChatGPTとGoogle Bertの世間の注目度の大きな違い。
ChatGPTは、2022年11月30日に公開され、2か月で1億人のユーザーを獲得した。Bertは、2018年に公開され、2019年にはGoogle検索に適用されていた。しかし、テキスト生成ができなかったため、注目を浴びることはなかった。
Googleは、すべての技術を作り、先行していたにもかかわらず、成果を回収できなかった。その違いは、公開の仕方にあった。
知能について
人間の知能を研究するために、AIの研究は続けられてきた。それでは、大規模言語モデルの生成AIがその回答なのだろうか?チューリングテストに合格すれば、それでいいのか?
確かに著者が言うように、生成AIは人間の知能をシミュレーションしているが、それだけで解明できたとは言えない。脳というハードウェア中で混然一体となった活動が、可塑性、発想力、直感などを生み出しており、そこまでは生成AIでも対応できているわけではない。コンピュータというハードウェアとソフトウェアという2つに分離できるものではない、と著者は言う。
人間の知性を研究するならば、著者の言う通りだろう。しかし、人間の知性をシミュレーションする装置を作ったら、人間以上のことができるようになった。それの限界を調べてみようというのが、学者ではなく、一般の人間だろう。
鳥が空を飛べるメカニズムを調べたが、実現できなかった。しかし、プロペラ機やジェット機を造ったら、鳥よりも高速に飛べるようになった。
それと同じように、人間の知能を真似た装置を作ったら、ある部分では人間以上の性能がでることがわかった。これの限界はどこまで行くのか確認したい。と誰でも思うことだろう。
本書の要約をChatGPTにお願いしてみた
田口善弘著「知能とはなにか ヒトとAIのあいだ」の要約
田口善弘氏の著書「知能とはなにか ヒトとAIのあいだ」は、中央大学理工学部教授である著者が、急速に進化する生成AIを背景に、「知能とは何か」という根源的な問いを物理学者の視点から深く考察した一冊です。
本書の主な内容は以下の通りです。
- 知能の定義の再考: 著者は、これまで曖昧だった「知能」の定義を根本から問い直し、人間の知能と人工知能(特に生成AI)の共通点と相違点を整理します。人間の知能は脳の新皮質で生み出される機能とされますが、その具体的な仕組みは未解明であり、知能の定義自体も定まっていない現状を指摘します。
- 生成AIの仕組みと限界: ChatGPTに代表される生成AIは、大規模言語モデル(LLM)などの深層学習によって、人間に近い知的ふるまいを実現しています。しかし著者は、これらのAIが本当に「考えている」わけではないと主張します。AIは膨大なデータからパターンを学ぶことで言語応答を可能にしているものの、人間の知能が持つ柔軟性や少ないデータから学習する能力とは異なる特性を持つと指摘します。
- 脳とAIの比較: 人間の脳と生成AIは、それぞれ異なる原理で動作し、異なる限界を持った「現実シミュレーター」として捉えることができると論じます。脳は少ないサンプルで効率的に学習できるのに対し、AIは膨大なデータを必要とします。この違いが、AIが自律的に改良を繰り返し人類を超えるという「シンギュラリティ(技術的特異点)」の仮説に対して、著者が懐疑的な立場を取る根拠となっています。
- 知能研究の今後: 本書は、AIが人類を上回る知能を持つか、シンギュラリティは起きるのかといった、今世紀最大の論点に物理学者の視点から挑み、AI時代における人間の立ち位置や、知能研究の今後の方向性についても考察しています。
この本は、AIに興味があるものの専門的な技術書はハードルが高いと感じる方や、AI時代における人間の知能のあり方について深く考えたい読者にとって、知的好奇心を刺激し、深い思索を促す一冊と言えるでしょう。専門的な内容を扱いながらも、平易な言葉で書かれており、幅広い読者層に推奨されています。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。